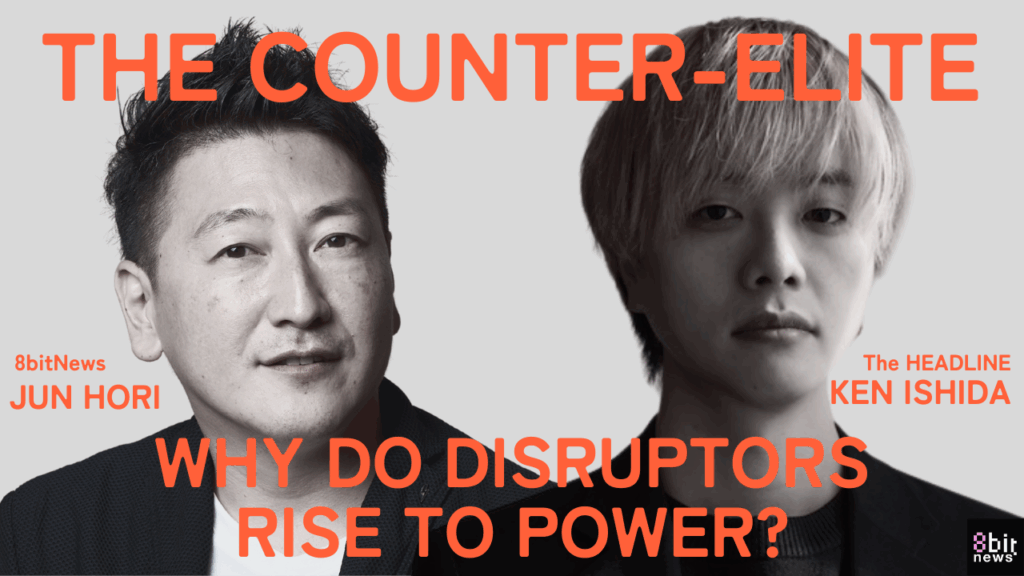「なぜ“破壊者”たちが支持を集めるのか?」。
この問いに正面から挑んだのが、起業家・評論家の石田健氏による新著『カウンターエリート』(文春新書)だ。8bitNewsスタジオで行われた堀潤氏との対談では、現代社会を覆う不信と混乱、そしてそれを打破しようとする動きについて、深く掘り下げる議論が展開された。
「カウンターエリート」とは、戦後続いてきた“リベラルな秩序”に異議を唱える存在だ。良い大学、良い会社、終身雇用、年金生活という「神話」の上に築かれた社会に対し、「そのルール自体が機能していない」と感じた人々が、破壊的なリーダーに共鳴していく。
石田氏はこの構造を、アメリカの投資家ピーター・ティールの発言に基づきながら分析する。ティール自身が移民でありLGBTであるにもかかわらず、なぜトランプ支持に傾いたのか。その背景にある「合理性」を探ることで、現代のポピュリズムを読み解こうとする。
番組内で繰り返されたのが「ナラティブ(物語)」というキーワードだ。
堀氏は「今の時代、ファクトよりも“共感できるストーリー”が選ばれる」と指摘する。視聴者が求めるのは、正確な情報ではなく、自分が信じたい世界を肯定してくれる語り。その流れの中でメディアは「ファンメディア化」し、多様な声や立場を排除する空気が強まっている。
「リアルな声を届けたいと現場に行っても、原発問題のように“反対派”とラベルを貼られる」と堀氏は語る。報道への信頼を取り戻すには、物語に呑み込まれず、「伝えることの多様性」を保つ必要があると強調した。
話題は、リベラル・デモクラシー(自由民主主義)の限界にも及んだ。
「戦後の民主主義は、理念として支持されてきたわけではない。経済成長していたから、それで良しとされてきただけではないか」。石田氏はそう問いかける。経済の低成長が常態化した今、その制度の正当性が揺らいでいる。
一方で、アメリカは「政治の実験国家」として、破壊的な変化を許容してきた。イーロン・マスクの「SpaceX村」のように、企業が都市を支配し、自律的な社会実験を行うような動きも登場している。国家がスタートアップのように動く危うさと可能性が、同時に語られた。
堀氏は、自身が8bitNewsを立ち上げた背景として「既存メディアが伝えきれない声への苛立ちと、自ら現場で伝える責任感」を語った。
石田氏もまた、自らの分析が「ただの知識ではなく、現代社会を考える武器になってほしい」と語る。
「破壊者」として現れるカウンターエリートたちは、単なる怒りの代弁者ではない。彼らの存在が突きつけるのは、私たち自身の価値観と向き合うことの必要性だ。
対談の最後に堀氏はこう語った。
「真っ当な社会にしたいという思いがあっても、物語が先行しすぎる今、何が正しいのか見えにくくなっている。だからこそこの本は、今の時代を読むための“教科書”になる」
混沌とする世界の中で、社会の構造とその変化を読み解くヒントが詰まった『カウンターエリート』。
その議論は、私たち一人ひとりに「あなたはどの立場で、何を変えたいのか?」と問いかけてくる。
※文春新書『カウンターエリート』 著:石田健
※8bitNewsスタジオ配信:YouTube「Ken Ishida × Jun Hori “The Counter-Elite”」